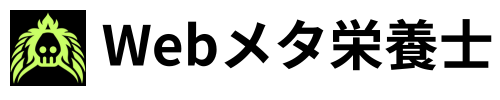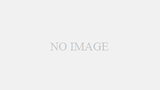脳腸相関(のうちょうそうかん)とは、脳と腸が自律神経やホルモン、サイトカイン(細胞から分泌されるたんぱく質)、神経伝達物質などを介して双方向に情報をやり取りし、互いに影響を及ぼし合う関係を指します。
脳腸相関の特徴
- 双方向のコミュニケーション
- 脳がストレスや感情を感じると、自律神経を通じて腸に影響が及び、腸の動きや消化機能が変化します。
- 逆に、腸の状態(不調や炎症など)が神経やホルモンを介して脳に伝わり、気分や行動にも影響を与えます。
- 腸の独自性
- 腸は「第二の脳」とも呼ばれ、脳からの指令がなくても独自に活動できる神経ネットワークを持っています。
- 腸内細菌の関与
- 腸内に生息する細菌(腸内細菌叢・マイクロバイオーム)も、神経伝達物質や代謝物を介して脳に影響を与えます。
- 腸内細菌がセロトニンなどの神経伝達物質の合成に関わっていることも知られています4。
- 健康への影響
- 脳腸相関が乱れると、ストレス性の胃腸障害や過敏性腸症候群(IBS)、抑うつや不安などの精神的な不調が現れることがあります。
- 最近では、脳腸相関が認知症やアルツハイマー病の発症・進行にも関与している可能性が指摘されています。
具体例
- ストレスを感じるとお腹が痛くなる
- 腸の不調が抑うつや不安を引き起こす
- 腸内細菌のバランスが脳の健康や認知機能に影響する
まとめ
脳腸相関は、脳と腸が密接に連携し、精神・身体の健康に重要な役割を果たしている仕組みです。腸内環境を整えることが、ストレス対策や認知症予防など、健康維持に役立つと考えられています。