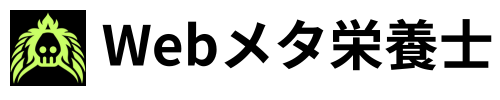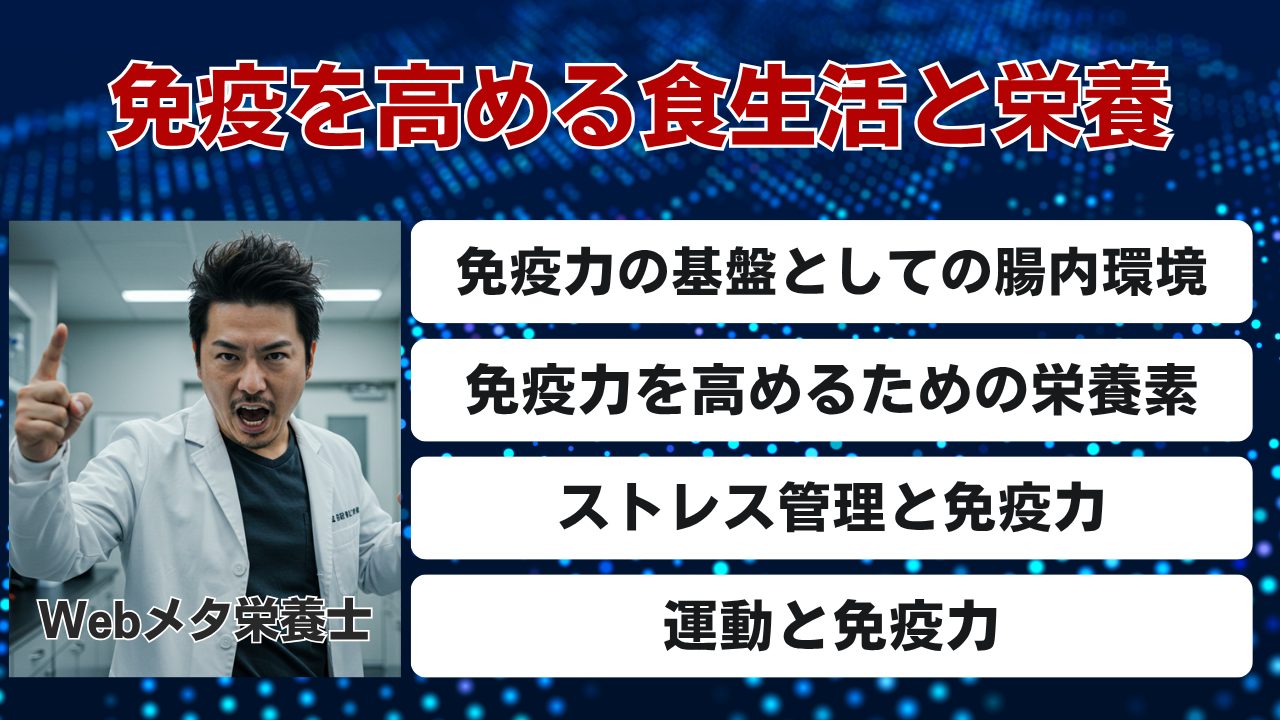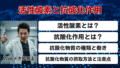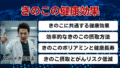1. 免疫力の基盤としての腸内環境
免疫力維持において腸内環境の健康が非常に重要であると複数の情報源が強調しています。
- 善玉菌の役割:
最近では「腸の健康を保つことが免疫力を高める鍵」であり、「そのためには腸内の善玉菌を増やすことが大事です」とよく耳にすると思います。善玉菌は私たちの身体の調子を整えてくれますが、そのはたらきの一つに免疫細胞の活性化があります。 - 発酵食品の摂取:
善玉菌を増やすための具体的な方法として、発酵食品の積極的な摂取が推奨されています。発酵食品にはこの善玉菌が豊富に含まれるので、食べることで直接摂取することができます。
具体的な発酵食品として、漬物、納豆、チーズ、味噌、かつお節、醤油、酢、みりん、甘酒、ヨーグルトなどが挙げられています。
ヨーグルトに含まれるビフィズス菌などの善玉菌は、腸内環境を整え、免疫力を高める効果が期待されます。
発酵食品は血行促進や代謝向上作用も期待でき、ダイエット効果も示唆されています。 - 腸内細菌叢とストレス:
ストレスが腸内細菌のバランスを変化させ、腸粘膜の免疫の乱れを引き起こすことがマウスの実験で示されており、慢性的なストレスによる腸疾患の発症には腸内細菌叢の乱れが関与している可能性が示唆されています。
※腸内細菌叢
腸内に棲んでいる細菌は、菌種ごとの塊となって腸の壁に隙間なくびっしりと張り付いています。この状態は、お花畑(flora)にみえることから「腸内フローラ」と呼ばれるようになりました。正式な名称は「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」です。
2. 免疫力を高めるための主要な栄養素と抗酸化物質
免疫機能の維持・向上には、バランスの取れた栄養摂取が不可欠です。特に、以下の栄養素と抗酸化物質が強調されています。
- 五大栄養素の重要性:
栄養のバランスと免疫力は関係しており、「炭水化物(糖質)」「たんぱく質」「脂質」「ビタミン」「ミネラル」の五大栄養素が免疫機能との関わりにおいて重要です。 - ビタミンA:
粘膜で病原体と戦うIgA抗体を作るためにビタミンAが力を発揮し、その強い抗酸化力で病原体による炎症を局所で抑え込むと言われています。βカロテンが腸でビタミンAに変換されます。うなぎ、銀だら、あなご、チーズ、卵、のり、しそ、モロヘイヤ、にんじん、ほうれん草などに豊富に含まれています。 - ビタミンC:
抗酸化作用を持ち、免疫細胞が病原体を殺す際に発生する活性酸素から体を守る働きがあります。また、免疫細胞を助ける働きも兼ね備えています。
厚生労働省eJIMのビタミンCに関する資料によると、果物と野菜が優れた供給源であり、特に柑橘類、トマト、じゃがいも、赤・緑ピーマン、キウイフルーツ、ブロッコリー、イチゴ、芽キャベツ、などが挙げられています。
ビタミンCは水溶性で熱に弱く、長期保存や調理で減少する可能性があるため、生で食べられる食品から摂取することが推奨されています。
喫煙者や受動喫煙者は酸化ストレスが増加するため、非喫煙者より多くのビタミンCが必要であるとされています。
濃縮乳や煮沸乳を与えられている乳児、食品の種類が限られている人(高齢者、貧困者、アルコール・薬物乱用者、精神疾患のある人、一部の小児など)、吸収障害や特定の慢性疾患を持つ人はビタミンC不足のリスクが高いとされています。 - 抗酸化物質(全般):
風邪やインフルエンザなどの感染症時には、炎症と戦う抗酸化物質をしっかり摂ることで、早期回復が期待できると小児科医は述べています。新鮮な魚や野菜などの抗酸化力の高い食材が良いとされています。
抗酸化作用のある食材を意識して摂取することが免疫力アップのポイントとです。 - 大塚製薬は、植物由来の抗酸化物質ポリフェノールの一種であるアントシアニンが免疫物質IgAを増やす働きがあることを指摘しています。ニュージーランドカシスのエキス摂取により、運動による酸化ストレス後でも唾液中のIgA分泌量が増加し、粘膜免疫を維持できた研究結果が示されています。アントシアニンはカシス、ブルーベリー、ぶどう、紫キャベツ、ナスなどに含まれます。
- はちみつ: 咳や鼻水などの症状を抑える効果が示されており、抗菌作用や抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれているため、炎症を抑える作用が期待されます。
※赤ちゃんのお母さん・お父さんやお世話をする方へ
・1 歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがあります。
・ ハチミツは1歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品です。
・ボツリヌス菌は熱に強いので、通常の加熱や調理では死にません。1歳未満の赤ちゃんにハチミツやハチミツ入りの飲料・お菓子などの食品は与えないようにしましょう。 - その他:
・にんにくはアリシンを含み、免疫力を高める作用があるとされています。
・バナナは体力回復を助け、免疫力を高める効果が期待されます。
・ブロッコリー、菜の花、柑橘類はビタミンCが豊富で、抗酸化作用により免疫細胞を助ける働きがあります。
3. ストレス管理と免疫力
ストレスは免疫力低下の主要な要因であることが強調されています。
- IgA分泌の低下:
強いストレスを受け続けると自律神経のバランスが乱れ、鼻、口、呼吸器などの粘膜で働く免疫物質IgAの分泌量が低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなると言われています。 - 慢性的なストレス:
学校や仕事場などからの慢性的なストレスが唾液中のIgAを低下させることが研究で示されています。 - 急性的なストレス:
短時間の心理的ストレス(暗算課題)や物理的ストレス(寒冷ストレス)でも、IgA分泌率が著しく低下することが報告されています。これは、たとえ短い時間でもストレスが免疫力に悪影響を及ぼすことを示しています。 - ストレス解消の重要性:
最近ではストレスを溜めないことが免疫力向上につながると言われており、リラックスできる時間を持つことや趣味に没頭することなどを推奨しています。
※ストレスを溜めないようにって言われても、それが簡単に出来ないんですよねえ。
4. 運動と免疫力
適度な運動は免疫力の向上に効果があると、多くの研究で報告されています。
適度な運動が免疫力を高める理由
- 筋肉を動かすことで体温が上がり、血行が良くなるため、全身に酸素や栄養が行き届きやすくなります。
- 血液やリンパの流れが促進されることで、免疫細胞が体内を効率よく巡回し、ウイルスや細菌などの病原体を早期に発見・排除しやすくなります。
- 唾液中のIgA(免疫物質)分泌量が増加し、風邪などの感染症にかかりにくくなることが示されています。
どんな運動が「適度」なのか
- 毎日60分程度、積極的に体を動かす(歩く、掃除、犬の散歩など)
- 週2回以上、1回30分以上の息が少しはずむ程度の運動(速歩き、軽い筋トレ、ラジオ体操など)
- 30分~60分程度の中強度の有酸素運動(ウォーキングやジョギング)が特に効果的とされています。
注意点
- 激しすぎる運動や長時間の過度な運動は、逆に免疫力を低下させることが分かっています。これは、ストレスホルモン(コルチゾールなど)が分泌され、免疫細胞の働きを抑制してしまうためです。
5. 高齢者の低栄養とその予防
高齢者の低栄養は、身体機能の低下、生活機能の低下、そして最終的に要介護状態に繋がる深刻な問題です。
- 低栄養の実態:
大阪公立大学の研究は、大規模コホート分析により、地域在住高齢者の低栄養(血清アルブミン値3.5g/dl以下)の発症率が年齢とともに顕著に高まることを明らかにしました。特に90歳以上では、男性で19.0%、女性で11.1%に達します。 - 「60歳代の高齢者の中にも低栄養状態に陥っている人が存在すること」も指摘されています。
- アルブミン値の低下: 血清アルブミン値は加齢とともに統計的に有意に低下することが示されています。これは、加齢が低栄養状態に影響する要因であることを示唆しています。
- 低栄養のリスク要因:
食欲低下、唾液分泌・咀嚼能力・味覚・嗅覚機能の低下、消化吸収機能の低下、筋肉減少症などの身体的要因に加え、配偶者の死、孤独感、うつ、認知症などの心理的要因、経済的貧困、独居、居住地域特性、調理や買い物の困難などの社会的要因、嚥下障害、炎症、悪性腫瘍、慢性疾患、薬の副作用などの疾病要因が複合的に関与し、食事摂取量の低下を引き起こします。 - 健康行動による予防:
定期的な健康診査の受診回数が多い高齢者ほど、血清アルブミン値が高い傾向にあることが示されました。これは、健康意識の高い人が日常的に健康維持のための具体的な行動(食事や運動など)を行っている可能性を示唆しており、健診受診が低栄養の予防に繋がると結論付けられています。 - 一口量の配慮:
大阪公立大学の研究では、嚥下困難者用ゼリー状食品の「至適1回嚥下量」が年齢とともに増加する傾向があることを明らかにしました。これは、高齢者が嚥下反射などの神経系の加齢変化により、より多い量で嚥下反応が引き起こされるためと推察されます。
「高齢者が楽しく、気持ちよく食事を行うためには、少し多めの一口量を食べさせる方がよい」可能性が示唆されており、安全で容易に食事をするための介護者の配慮の重要性が強調されています。
※ただし、「多ければ多いほど良い」という意味ではありません。
「至適量」とは、その人が安全かつ楽に飲み込めるちょうど良い量を指します。
一度に入れる量が多すぎると、当然ながら誤嚥(気管に入ること)のリスクが高まります。
この研究が示唆しているのは、「高齢者の嚥下ケアでは、本人にとって飲み込みやすい一口量を見極めることが大切」という点です。
介護現場では「少し多めの一口量が適している場合もある」ことを理解しつつ、個々の嚥下機能に合わせて量を調整することが重要です。
要するに、「高齢者は必ず少量ずつでなければならない」という固定観念にとらわれず、安全を最優先しつつ、その人に合った一口量を探ることが、誤嚥を防ぎ、楽しく食事をするために大切ということです。
6. 全体的な健康維持のポイント
上記の詳細に加えて、以下の全体的なポイントも免疫力と健康維持に重要です。
- 水分補給:
「こまめに水分補給をする」ことを免疫力アップのポイントとして。水分補給が乾燥と粘膜免疫に関係しているからだと考えられています。 - 良質なたんぱく質の摂取:
主菜として「良質なタンパク質(必須アミノ酸をバランスよく摂ることのできるもの)を多く含む肉や魚を使って、タンパク質やミネラルを補うことが大事です。 - 多様な食材の摂取:
「カラフルな野菜と果物を毎食取り入れる」こと、「旬の緑黄色野菜を中心に、淡色野菜や海藻、きのこ、芋類など、できるだけ多品目の食材を使ったミネラル・食物繊維たっぷりのお惣菜を摂ることも推奨されています。 - 睡眠の質:
適切な睡眠時間と睡眠の質が免疫力に影響すると言及している専門家も多いです。十分な睡眠が免疫力維持に重要であると述べています。
これらの情報源は、免疫力向上と健康維持が、単一の要素ではなく、食事、特定の栄養素、ストレス管理、運動、そして高齢者特有の課題への対応といった多角的なアプローチによって達成されることを示唆しています。