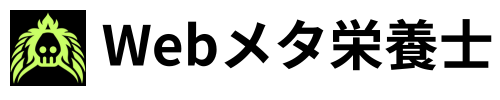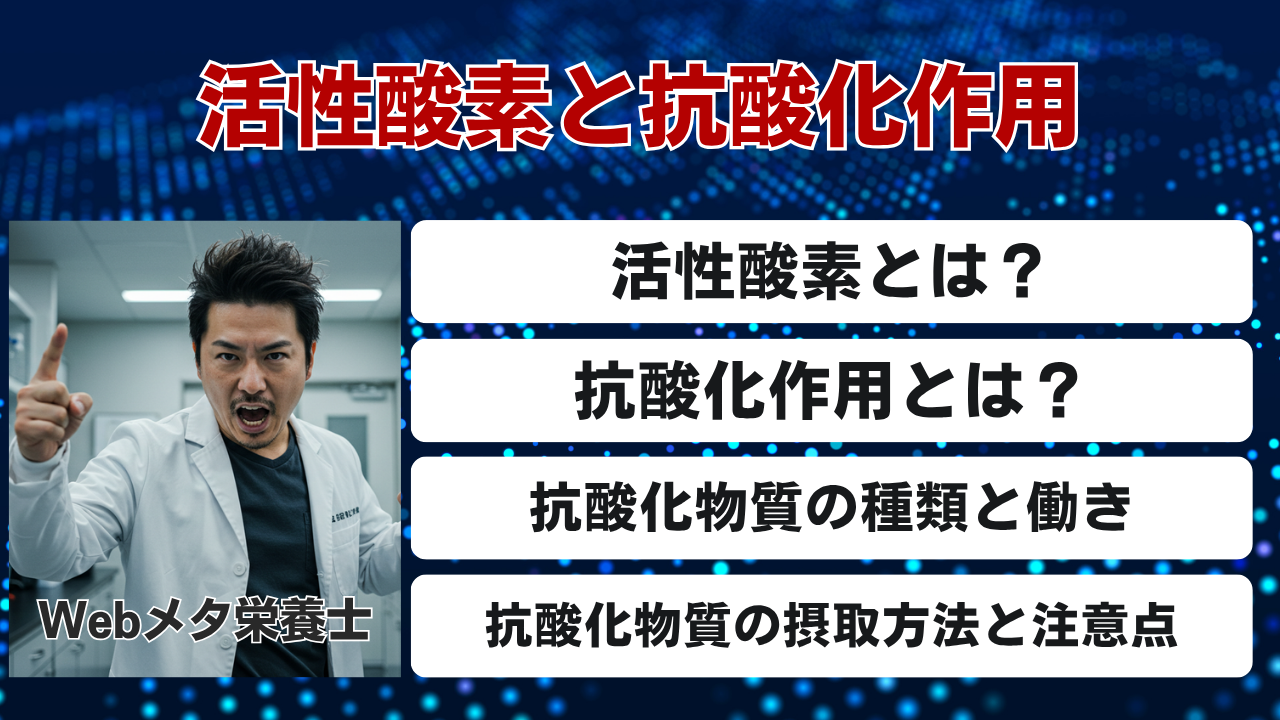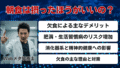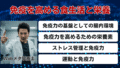体の酸化から健康を守る
活性酸素とは?
私たちは呼吸を通じて酸素を取り込み、食事で得た栄養素を燃やしてエネルギーを生み出しています。この生命維持の過程で、取り込んだ酸素の一部が「活性酸素」へと変化します。活性酸素は、「酸化する力」を持ちます。
活性酸素は、体内に侵入した細菌やウイルスの攻撃から体を守る重要な物質です。しかし、その酸化力が非常に強いため、体内で過剰に発生しすぎると、正常な細胞まで攻撃してしまうという特徴があります。
活性酸素が発生する主な原因
活性酸素の発生には、以下のような様々な要因が関係しています:
- 環境汚染物質(ダイオキシン、排気ガスなど)
- 食品添加物
- 過剰な紫外線
- 過度なストレス
- 喫煙
- 激しい運動
- 食べ過ぎ
- 放射線
- 電磁波(パソコン、電子レンジ、電気毛布など)
- 偏った食事
- 睡眠不足
活性酸素の種類
代表的な活性酸素の種類には、以下のものがあります:
- スーパーオキサイド (スーパーオキシドアニオン)
- 過酸化水素
- 一重項酸素
- ハイドロキシラジカル (ヒドロキシルラジカル) 特にヒドロキシラジカルは、活性酸素の中で最も毒性が強いとされています.
活性酸素が体に与える影響
活性酸素は不安定な状態にあるため、安定するために他の物質と結合しようとして、体内の組織や細胞を攻撃します。この攻撃によって細胞膜の脂質が酸化され、「過酸化脂質」が生成されます。さらに、過酸化脂質が新たな活性酸素を生むという悪循環も起こり得ます。
過剰な活性酸素は、以下のような様々な健康問題と深く関わっています:
- がん
- 動脈硬化
- 炎症
- 生活習慣病(糖尿病、脂質異常症など)
- 肝疾患
- 消化器疾患
- シワ、シミ
- 疲労
- 免疫力の低下
- 細胞損傷や細胞死
抗酸化作用とは?
「抗酸化作用」とは、体内で増えすぎた活性酸素を除去し、それによる細胞の損傷や体の「酸化(サビつき)」を抑える働きを指します。
体に備わる抗酸化システム
ヒトの体にはもともと、過剰に発生した活性酸素を無害化するシステムが備わっています。この主要な構成要素は「抗酸化酵素」と呼ばれる酵素群です。
主な抗酸化酵素には以下のものがあります:
- SOD(スーパーオキシドジスムターゼ)
- グルタチオンペルオキシダーゼ
- カタラーゼ
これらの酵素は、体内で合成され、活性酸素を無毒化してくれます。しかし、これらの酵素を作り出す体の力は、年齢とともに衰えていくことが知られています。そのため、体内の抗酸化作用をサポートすることが重要になります。
抗酸化物質は、酸化されやすい性質を持ち、自らが酸化されることで体を活性酸素の攻撃から守ります。また、抗酸化酵素の生成や活性に関与し、その効果を高める働きもします。
抗酸化物質の種類と働き
抗酸化作用を持つ物質は、酵素だけでなく、ビタミンやミネラル、その他の天然成分など色々あります。
酵素
- SOD(スーパーオキシドジスムターゼ): 主成分はタンパク質であり、亜鉛、銅、マンガンなどのミネラルを補因子として含みます。スーパーオキサイドを酸素と過酸化水素に分解します。
- グルタチオンペルオキシダーゼ: 主成分はタンパク質で、セレンを補因子として含みます。過酸化水素や有機ヒドロペルオキシドを分解し、無毒化します。
- カタラーゼ: 主成分はタンパク質で、鉄とマンガンを補因子として含みます。過酸化水素を水と酸素に変換します。
これらの酵素は、その主成分がタンパク質であるため、良質なタンパク質を食事から摂取することが、酵素を作り出す上で非常に大切です。
ビタミン
- β-カロテン(ビタミンA):活性酸素の発生を抑え、除去する働きがあります。体内で必要に応じてビタミンAに変換されます。レバー、うなぎ、モロヘイヤ、人参、かぼちゃ、春菊、ほうれん草、小松菜、ピーマン、ブロッコリーなどに豊富に含まれます。生では吸収されにくいため、油と一緒に摂ると吸収率が向上します。
※脂溶性ビタミンとは - ビタミンE:細胞内に過酸化脂質が作られるのを抑える働きが強い抗酸化物質です。アーモンド、ニジマス、ヘーゼルナッツ、うなぎ、かぼちゃ、落花生、モロヘイヤ、植物油、種子類、ほうれん草、ブロッコリーなどに多く含まれます。β-カロテンやビタミンCと協力して働くことで、抗酸化作用がより長持ちし、相乗効果が期待できます。
- ビタミンC:活性酸素の抑制に働き、強い抗酸化力で細胞や組織を活性酸素から守ります。ビタミンEを酸化型から還元型にリサイクルする働きもあります。柿、キウイ、赤ピーマン、いちご、オレンジ、ブロッコリー、カリフラワー、レモン、さつま芋などの野菜や果物、芋類に多く含まれます。体内では作られないため、毎日摂取が必要です。
ミネラル
ミネラルは抗酸化酵素の生成や活性に関わり、その効果を高めます。
- 亜鉛:SODの主成分の一つであり、細胞の新生を促します。牡蠣、牛肉、豚肉、うなぎ、ラム肉、いわしの丸干しなどに含まれます。
- 銅:SODの活性を促進します。牛レバー、ホタルイカ、イイダコ、干しエビ、ココア、牡蠣、カシューナッツなどに含まれます。
- セレン:過酸化脂質を分解し、無害化する働きがあります。マグロの刺身、ワカサギ、長ネギ、ホタテ貝、しらす干し、いわしの丸干しなどに含まれます。
- マンガン:SODの材料であり、細胞の酸化を防ぐ働きがあります。栗、ヘーゼルナッツ、玄米ご飯、そば、松の実、アーモンド、干し柿、生姜などに含まれます。
その他の抗酸化成分
- ポリフェノール:カテキン、アントシアニン、イソフラボン、クルクミンなどが含まれ、いずれも抗酸化力があるといわれています。緑茶、コーヒー、ぶどう、大豆製品、玉ねぎなどに多く含まれます。
- カロテノイド:α-カロテン、β-クリプトキサンチン、ルテイン、リコペン、アスタキサンチンなどが含まれ、活性酸素の発生を抑える他、皮膚や粘膜の働きをサポートするとされています。緑黄色野菜、マンゴー、パパイヤ、柿、すいか、海藻類、エビ・カニなどに含まれます。
- コエンザイムQ:ビタミンと同様の働きをして、ビタミンを助ける成分です。強い抗酸化力があり、アンチエイジングに役立つとされています。イワシ、サバ、牛肉、豚肉などに多く含まれます。
- 尿酸:ヒトの血中に最も高濃度で存在する抗酸化物質の一つであり、ヒト血清中の抗酸化物質全体の約半分を占めるとも言われています。
しかし、尿酸値が高い=アンチエイジングになる、とは言えません。
※尿酸 - メラトニン:細胞膜や血液脳関門を容易に通過できる強力な抗酸化物質です。他の抗酸化物質とは異なり、酸化還元サイクルを形成せず、一度酸化されると還元されずに安定な状態になるため「末端抗酸化物質」とも呼ばれます。
- ウロビリノーゲン:ヘモグロビンの代謝物で、抗酸化作用を有することが報告されています。
- メラノイジンとカラメル:メイラード反応やカラメル化によって食品中に生成される褐変物質で、抗酸化作用を持つことが知られています。特に味噌のラジカル捕捉能力は、その大半をメラノイジンが担っているとされます。
抗酸化物質の摂取方法と注意点
バランスの取れた食生活が重要
抗酸化酵素を作り出す栄養素は、単独で摂取するよりも、様々な食品を組み合わせてバランス良く摂取した方が、体内でより効率よく働くことが分かっています。野菜や果物には多くの抗酸化物質が含まれています。
過剰摂取のリスクと活性酸素の「善玉」の側面
※善玉・・体にとって良い働きをするもの
※悪玉・・体にとって悪い働きをするもの
従来、活性酸素は老化や生活習慣病の原因因子として「悪玉」と見なされ、除去することが体に良いと考えられてきました。そのため、多くのスポーツ選手や健康志向の人々が積極的に抗酸化物質を摂取しています。
しかし、近年の研究では、活性酸素が生体内で重要な生理機能も担っていることが分かってきました。特に脳においては、活性酸素を作る酵素が存在し、記憶学習の持続化に必要であることが示されています。
例えば、マウスを用いた実験では、抗酸化物質の一種であるビタミンEを過剰に投与すると、ある種の運動学習が顕著に阻害されることが示されました。これは、過剰な抗酸化物質の摂取が、記憶学習に必要な「善玉活性酸素」まで除去してしまう可能性があることを意味します。
サプリメント摂取に関する注意
サプリメントによる抗酸化物質の過剰摂取は、必ずしも有益とは限りません。一部の研究では、β-カロテン、ビタミンA、ビタミンEなどのサプリメントの過剰摂取が、特に喫煙者など特定のリスクが高い人において、肺がんのリスク増加や死亡率の増加につながる可能性が報告されています。また、ビタミンEの大量摂取は、出血のリスクを高めたり、特定の医薬品と相互作用を起こす可能性もあります。
野菜や果物を多く摂取する人は慢性疾患のリスクが低いという多くのエビデンスがある一方で、抗酸化サプリメントががんや心血管疾患の予防に明確な効果を示さない、あるいは有害である可能性が示唆される研究結果もあります。これは、食品からの摂取とサプリメントによる摂取では、体内の働きが異なる可能性があるためです。
※サプリメント摂取自体が悪いということではありません。食品から摂る方が理想とされていますが、摂れない場合は適正にサプリメントを使用するというのも間違った選択ではありません。
まとめ
活性酸素は、体内で生成され、免疫機能に役立つ一方で、過剰になると細胞を傷つけ、老化や様々な疾患の原因となります。私たちの体には活性酸素を無毒化する抗酸化システムが備わっていますが、その力は年齢とともに衰えるため、食事から抗酸化物質を補うことが重要です。
ビタミン(β-カロテン、ビタミンE、ビタミンC)、ミネラル(亜鉛、銅、セレン、マンガン)、そしてポリフェノールやカロテノイドなど、多様な抗酸化物質が知られており、これらを様々な食品からバランス良く摂取することが効果的です。
しかし、活性酸素には記憶学習など体内で重要な生理機能を持つ「善玉」の側面もあるため、抗酸化物質の過剰な摂取は、かえって体の正常な機能を妨げる可能性があることにも留意が必要です。サプリメントの摂取を検討する際は、必ず信頼できる情報源から情報を得て、医療専門家に相談するようにしましょう。
バランスの取れた食生活と適切な生活習慣を見直すことが、健康的な日々を過ごし、体の酸化を防ぐための鍵となります。