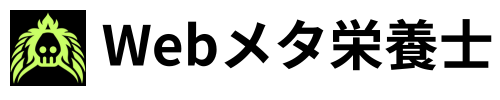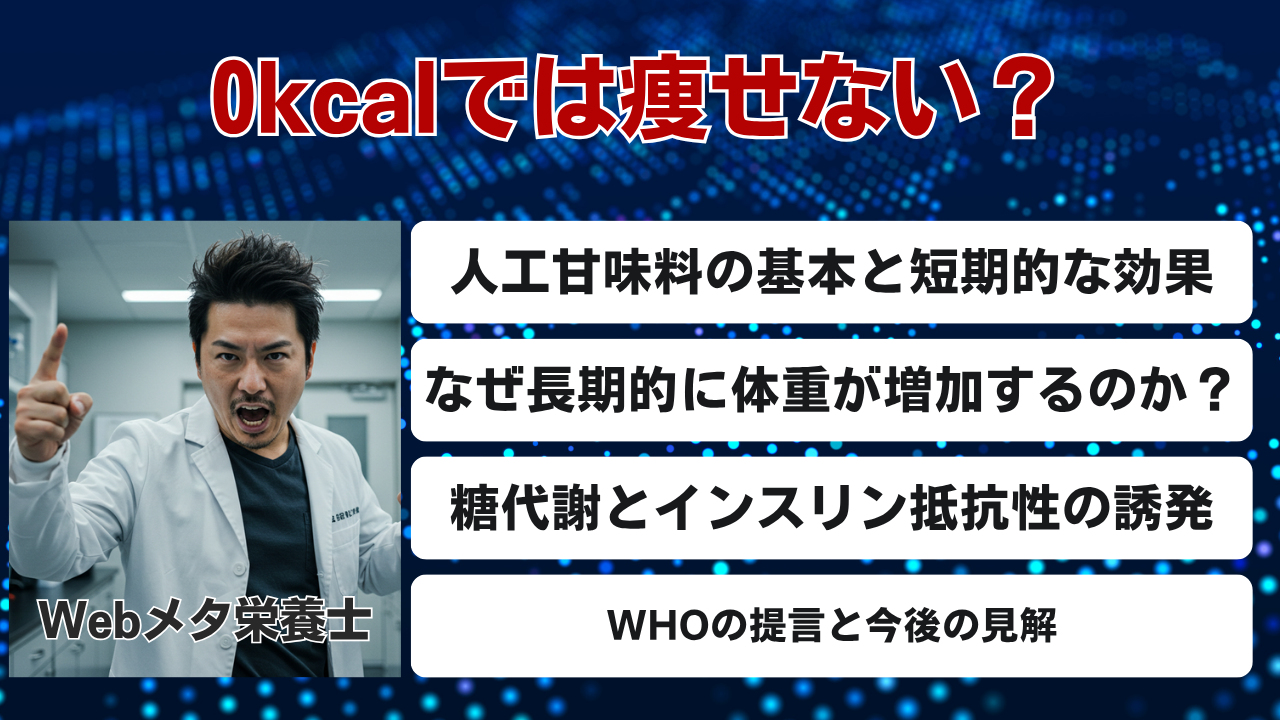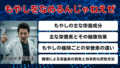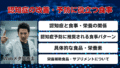人工甘味料と体重増加のメカニズム:長期的な影響と健康への懸念
人工甘味料は「0kcal」や「低カロリー」と謳われ、砂糖の代替品として広く利用されていますが。短期的には減量効果が示唆される一方で、長期的な摂取がむしろ体重増加につながる可能性が複数の研究で指摘されています。2023年5月、世界保健機関(WHO)は、減量や生活習慣病の予防のために人工甘味料(非糖質系甘味料)を使用しないよう提言しました。これは、長期的な研究から肥満や2型糖尿病、心血管疾患、全死亡リスクの増加との関連が示唆されたためです。
人工甘味料の基本と短期的な効果
人工甘味料は、アスパルテーム、アセスルファムカリウム(アセスルファムK)、スクラロースなどが代表的です。アスパルテームは1グラムあたり4キロカロリーの熱量がありますが、砂糖の200倍もの甘さがあるため、ごく少量で甘みを実現できます。アセスルファムKやスクラロースは1グラムあたりの熱量が0キロカロリーとされています。
砂糖は体内でブドウ糖と果糖に分解され、血糖値が上昇し、インスリンが分泌されてブドウ糖が脂肪として貯蔵されるため、摂りすぎると体重増加につながります。一方、人工甘味料にはブドウ糖が含まれないため、摂取しても血糖値は上昇せず、インスリンも分泌されないため、直接的に脂肪として貯蔵されることはありません。この特性から、砂糖の代わりに人工甘味料を使用することで摂取カロリーを抑え、短期的には減量効果につながる可能性が示唆されてはいます。
なぜ長期的に体重が増加するのか?主要なメカニズム
短期間の研究では減量効果が認められることがある人工甘味料ですが、年単位にわたる長期的な研究では、むしろ人工甘味料の使用が多い方が体重増加を認めたと報告されています。これは、カロリーゼロという単純な側面だけでは説明できない複雑なメカニズムが関与していると考えられます。
体重増加につながる可能性のあるメカニズムとして、主に以下の点が挙げられます。
腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)の変化
人工甘味料の摂取は、腸内細菌叢の組成を変化させることが複数の研究で示されています。腸内細菌は、血糖値のコントロール、インスリン感受性、脂肪の貯蔵、食欲、炎症など、体全体の代謝機能に影響を与えることが知られています。
- 人工甘味料の摂取は、腸内の微生物バランスを崩し、例えば、エネルギー吸収の増加につながる短鎖脂肪酸の腸管内での増加を招き、耐糖能異常を誘発する可能性が指摘されています。
- 動物実験では、人工甘味料が特定の腸内細菌(Bifidobacterium、Lactobacillus、Bacteroides)のレベルを減少させたり、Akkermansia muciniphiliaを減少させてブドウ糖不耐症を招いたりする可能性が示されています。
- 肥満の小児で増加する傾向にあるFirmicutes菌が増加し、Bacteroidetes菌が減少するといった腸内細菌の構成変化も示唆されています。
- 腸内細菌によるアミノ酸代謝の変化が発がん性物質の生成につながる可能性も指摘されています。
味覚の変化と食行動への影響
人工甘味料の摂取は、甘味の知覚や好みを変化させ、結果として食行動に影響を与える可能性があります。
- 動物実験では、人工甘味料の摂取がカロリー摂取に対する通常の反応を変化させ、結果として過食につながる可能性が示唆されています。
- 「カロリーがない甘さ」に慣れることで、より甘いものへの欲求が高まったり、栄養価の高い自然な甘さを持つ食品(果物など)への魅力が低下したりする可能性があります。
- 人工甘味料の甘味が、消化管が栄養素の消化と利用に備える準備段階である頭相反応(とうそうはんのう)を抑制する可能性も指摘されています。この反応が適切に起こらないことで、その後の食行動や代謝に影響を及ぼすと考えられます。
糖代謝とインスリン抵抗性の誘発
人工甘味料自体は血糖値を直接上げませんが、長期間の使用は、健常者においてインスリン抵抗性や2型糖尿病の発症と関連する可能性が指摘されています。
- フランスでの10万人を対象とした追跡調査では、人工甘味料の摂取が多いグループで糖尿病となるリスクが69%も高くなることが報告されています。
- 人工甘味料は、腸管や膵臓などにある甘味受容体を介して、間接的にインスリン分泌やインスリン抵抗性に影響を与える可能性が示唆されています。
※人工甘味料自体が砂糖のようにインスリン分泌に関与しているということではなく、あくまで間接的にということです。 - 例えば、スクラロースはT1R3と呼ばれる甘味受容体の活性化を通じて、肝臓での活性酸素種の生成を促し、脂肪分解や小胞体ストレスを誘発し、炎症性サイトカインの増加を通じてインスリン抵抗性を促進する可能性があります。
WHOの提言と今後の見解
2023年5月、WHOは「非糖質系甘味料の使用に関するガイドライン」を公表し、減量や生活習慣病の予防のために人工甘味料を使用しないように提言しました。
- この勧告は、人工甘味料の長期的な使用が肥満に関する有益なエビデンスを示さず、むしろ2型糖尿病、心血管疾患、全死亡率のリスクを増加させる可能性があるという長期観察研究の結果を根拠としています。
- ただし、この勧告は糖尿病で治療中の患者には適用されません。人工甘味料は血糖値やインスリン分泌に直接影響を与えないため、糖尿病の食事療法においては有用とされています。
- WHOは、人工甘味料が必須の栄養素ではなく、それ自体に栄養価がないことから、砂糖の摂取量を減らす際には、果物のような自然な甘さの食品や、加糖されていない食品・飲料を選択することを推奨しています。これは、人工甘味料を含む食品が加工度の高い食品に多く含まれる可能性があり、全体的な食事の質を向上させるためには、そうした食品を減らすことが重要であるという考えに基づいています。
人工甘味料の健康への影響についてはまだ不明な点も多く、さらなる長期的な研究が求められています。0kcalだから安心と言って炭酸飲料などを多く摂取する人がいますが、これはやめた方がいいです。しかし、人工甘味料は太る可能性があると言っても、砂糖がたくさん使用されている飲料を飲むよりは太りにくいのは事実だと思います。
とりあえず、飲みすぎていたと自覚する人は控えていきましょう。