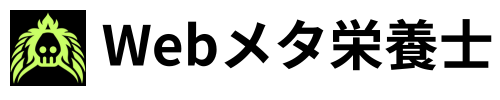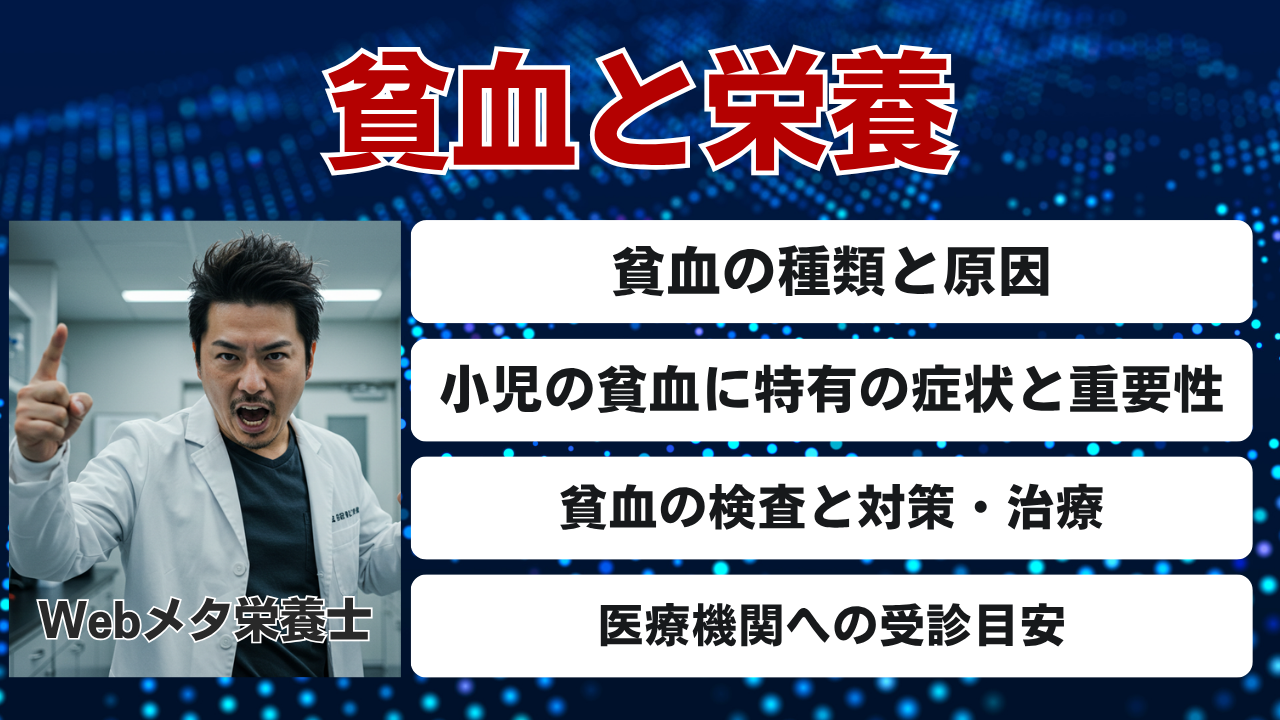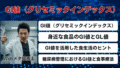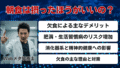1. 貧血の定義と診断基準
貧血とは、体に必要な酸素がうまく運ばれなくなる状態のことです。
これは、血液の中の「赤血球」や「ヘモグロビン(血色素)」といった、酸素を運ぶ役割のある成分が少なくなることで起こります。
血液1ミリリットルあたりに含まれる赤血球の数や、ヘモグロビンの量、血液の中で赤血球が占める割合(ヘマトクリット)が少なくなると、酸素を運ぶ力が足りなくなってしまいます。
世界保健機関(WHO)では、年齢や性別によって「これより少ないと貧血ですよ」という基準(ヘモグロビンの濃度)を決めています。
- 乳幼児(6~59ヶ月): 11 g/dL未満
- 子ども(5~11歳): 11.5 g/dL未満
- 子ども(12~14歳): 12 g/dL未満
- 妊娠していない女性(15歳以上): 12 g/dL未満
- 妊婦: 11 g/dL未満
- 男性(15歳以上): 13 g/dL未満
貧血の診断は主に血液検査のヘモグロビン値が基準となりますが、鉄欠乏の第一段階で減少する「血清フェリチン濃度」(貯蔵鉄の指標)も診断に効率的で費用対効果の高い検査とされています。「血清フェリチン濃度が30μg/Lより低いと鉄欠乏を、10μg/Lより低いと鉄欠乏性貧血を示唆する」とされています。
2. 貧血の種類と原因
貧血は様々な原因によって引き起こされ、その種類も多岐にわたります。
2.1. 鉄欠乏性貧血
- 原因: Hb(ヘモグロビン)の主な材料である鉄が不足することで起こります。これは、「鉄摂取量の不足、鉄需要の増加、過剰な鉄損失、鉄の吸収阻害」などが原因となります。
- 特徴: 血清鉄とフェリチン濃度が低く、鉄結合能が高い傾向があります。「小球性低色素性貧血の原因の大部分を占める」とされています。
※ 鉄結合能が高い=鉄が足りていないサイン
トランスフェリンが「鉄をもっと運ばなきゃ!」と頑張ることで、鉄を結合する能力(結合能)が高くなります。
つまり:
鉄結合能が高い=体に鉄が足りていないことが多いということ。 - 小児における特記事項:乳児期: 「新生児の造血は、妊娠後期に母体から移行した鉄に依存する」。生後4~6ヶ月頃までは母体からの移行鉄で十分ですが、それ以降は急速な成長に伴い鉄の需要が供給を上回るため、「生後6か月以降になると鉄の需要が供給を上回る。この時期に十分な鉄を摂取しなければ、鉄欠乏性貧血に陥る」。
- 牛乳貧血: 長期間にわたって大量の牛乳を摂取することで鉄分が不足し起こるもので、「牛乳は、鉄の含有量が非常に少ない」。乳児が1日に必要とする鉄は5mg程度に対し、牛乳は1リットルあたり約0.6mgしか含まれていません。
牛乳の飲みすぎが原因で、鉄が足りなくなって起こる貧血のことです。
とくに 乳幼児(1〜3歳ごろ) に起こりやすいです。
※ なぜ牛乳で貧血になるの?
① 牛乳には鉄がほとんど含まれていない
1リットルの牛乳に含まれる鉄 → 約0.6mg
乳児が1日に必要な鉄 → 約5mg
つまり、牛乳だけでは全然足りないんです。
② 牛乳ばかり飲むと「ごはんやおかず」を食べなくなる
食欲が牛乳で満たされて、鉄の多い肉や魚を食べる量が減る
結果として「食事からの鉄の摂取量が落ちる」
③ 牛乳の中のカルシウムやカゼインが「鉄の吸収を邪魔する」
牛乳に多く含まれるカルシウムやたんぱく質(カゼイン)は、
鉄の吸収をブロックする作用があることが知られています。
※ 鉄剤を飲んでいてなかなかHb値などが改善しない人は、飲み合わせや食べ合わせが悪いことも原因の一つです。服用のタイミングを見直すことで検査値が改善されることもあると思います。 - 思春期: 急激な成長による鉄需要の増加、ダイエットや偏食による食事摂取不足、女児の月経による失血が原因となります。
2.2. 再生不良性貧血
- 原因: 「骨髄で血液が造られないために血液中の赤血球、白血球、血小板のすべての血球が減ってしまう病気」です。「ほとんどの場合が原因不明だが、医薬品が原因となることもある」。
- 治療: 「造血幹細胞移植以外の治療ではATG(anti-human thymocyte immunoglobulin)+cyclosporineによる免疫抑制療法が基本」です。最近ではウマATGが認可され、トロンボポエチン受容体作動薬(eltrombopag、romiplostim)も使用可能です。HLA半合致移植の報告も増えています。
2.3. 悪性貧血(巨赤芽球性貧血)
- 原因: 「ビタミンB12や葉酸が欠乏することでDNA合成が障害され、赤血球の他に白血球や血小板なども減少し、骨髄に巨赤芽球が出現する」。
- 特徴: 赤血球のサイズが大きいことが特徴です。
2.4. 溶血性貧血
- 原因: 「赤血球の寿命よりも赤血球膜が早く壊れて起こる」。原因は自己免疫性、遺伝性など様々ですが、マラソン選手や長距離歩行などのスポーツ選手に起きることもあります。
- 種類: 先天性(遺伝性球状赤血球症、サラセミア症候群、G6PD異常症など)と後天性(自己免疫性溶血性貧血、発作性夜間ヘモグロビン尿症など)に大別されます。
- 自己免疫性溶血性貧血: 「自身の赤血球に結合する自己抗体ができて、赤血球が異常に早く破壊されておこる貧血」で、稀な病気です。
2.5. 腎性貧血
- 原因: 「赤血球産生の調節因子であるエリスロポエチンが腎障害によって腎臓で生産されなくなることで起きる」。
- 重要性: 慢性腎臓病(CKD)患者に見られ、進行すると心不全になるリスクがあり、死亡率の上昇とも関連する可能性があります。
2.6. 慢性疾患に伴う二次性貧血
- 原因: 慢性感染症、慢性炎症、悪性腫瘍などによる炎症性の貧血です。炎症性サイトカインにより肝臓からのヘプシジン産生が亢進し、鉄の利用が阻害されます。
- 特徴: 血清鉄やHbが低下する一方で、フェリチンが貯蔵鉄量とは無関係に増加する傾向があります。これは、炎症によってフェリチンが上昇するため、鉄欠乏の診断を困難にすることがあります。
長期にわたる慢性疾患でヘプシジンの分泌が過剰に維持されていた場合、炎症が治っても
鉄の出入りを調整する機構が鈍くなっておりすぐに改善しない場合がある。
2.7. その他の貧血
- 加齢による老人性貧血: 生体機能低下によって引き起こされます。
- 微量栄養素不足による貧血: 亜鉛や銅などの不足が原因となることがあります。
2.8. がん患者における貧血
- 直接的な原因: 消化管がんなどからの出血や、白血病、骨髄異形成症候群、がん細胞の骨髄浸潤によって貧血が起こることがあります。
- 治療による原因: 薬物療法や放射線治療による骨髄抑制、薬物療法による溶血が挙げられます。胃がん手術後は、ビタミンB12や鉄の吸収機能が低下し、数年後に貧血になることもあります。
- 栄養不足による原因: がんや治療の影響で食事が十分に摂れず、赤血球やヘモグロビンを作る栄養素が不足することがあります。
3. 貧血の主な症状
貧血は全身の酸素不足状態を引き起こし、様々な症状が現れます。
一般的な症状: 立ちくらみ、息切れ、めまい、ふらつき、頭痛、胸の痛み、倦怠感、疲れやすさ、顔面蒼白、動悸、眠気、集中力低下、耳鳴り。
特異的な症状:
- 味覚異常、舌の痛み、口角炎、口内炎: 鉄欠乏性貧血やビタミンB12、葉酸欠乏性貧血で見られることがあります。
- むずむず脚症候群(じっとしていると足がむずむずする): 貧血と関連する症状として挙げられています。
- 皮膚や白目の黄染: 溶血性貧血で、ヘモグロビンの分解産物であるビリルビンが溜まることで起こる黄疸の症状です。
- 氷食症: 鉄欠乏性貧血で無性に氷を食べたくなることがあります。
- 黒い便(タール便)や血を吐いた(吐血): 消化管からの出血を示唆する重要な兆候であり、「緊急の対応が必要になることがあります」。
- 症状とヘモグロビン値の関連: Hb値が8~9g/dl程度までは無症状の場合もありますが、7g/dl以下になると頭痛、耳鳴り、めまい、疲れやすさなどが顕著になり、6g/dl以下が続くと息切れや息苦しさなどの心不全症状を起こしやすくなります。「Hbが6〜7g/dl程度になると心不全の症状が起こるようになり、輸血が必要となることが多い」とされています。
- 急性貧血と慢性貧血の症状の違い: 急性の貧血(急性出血など)は「とてもしんどい」と感じられ緊急疾患ですが、慢性の貧血は体が適応するため「意外と元気」なことが多いです。
4. 小児の貧血に特有の症状と重要性
小児、特に乳児は自分で症状を訴えることができないため、貧血の発見が遅れがちです。
- 乳児の症状: 「顔面蒼白」「体重増加不良」「哺乳不良」「不機嫌」「頻脈」「元気がない」。
- 中枢神経系の発達への影響: 「特に乳児期の鉄欠乏は、長期的な中枢神経系の発育・発達に影響を与える」とされ、「貧血に至る前に、神経発達への悪影響など気づきにくい病態を未然に防ぐことが重要」です。「鉄欠乏では脳内神経伝達物質の生合成がうまく行われなくなる」。
- 注意欠如・多動症(ADHD)との関連: 「注意欠如・多動症(ADHD)のこどもは、鉄欠乏がないか確認しましょう」とされており、ADHD患児の84%で血清フェリチン濃度が低い(30ng/mL未満)という報告もあります。
鉄は脳の神経伝達に関与しており、ADHDとの関連が研究されています。特に鉄不足があるADHD児に限って、鉄補充が症状改善に役立つことがあります。ただし、「鉄を摂ればADHDが治る」という単純な話ではありません。
必ず医師と相談の上で血液検査を行い、必要に応じた治療を受けましょう。 - 思春期: 急激な成長、ダイエットや偏食、月経による失血が原因となります。身体のだるさ、朝起きられない、集中力低下、抑うつ症状などが見られる場合は鉄不足が隠れている可能性があります。
5. 貧血の検査と対策・治療
貧血対策は、原因に対する治療が最も重要です。
5.1. 検査
- 採血: ヘモグロビン値、ヘマトクリット、赤血球数、血清鉄、フェリチン(貯蔵鉄)、鉄結合能などの項目が測定されます。
- 目の結膜の確認: 「眼瞼結膜(がんけんけつまく=まぶたの裏側の粘膜)が蒼白な場合」は貧血が疑われます。
- 爪の形状: 「爪が反り返っている(スプーン爪)場合」は、鉄欠乏性貧血が疑われます。
5.2. 栄養療法
貧血対策になる栄養素をバランスよく摂取することが推奨されます。
- 鉄: ヘム鉄(肉、魚介類)と非ヘム鉄(植物性食品)があり、ヘム鉄の方が2~3倍吸収されやすいです。非ヘム鉄の吸収は、”ふすま”やフィチン酸、お茶や野菜に含まれるポリフェノールなどによって阻害されることがあります。
- 鉄を多く含む食品: 鶏レバー、ひじき、ホウレン草、小松菜、カキ、アサリ、切り干し大根、大豆、高野豆腐、がんもどき、納豆、カツオ、菜の花、小豆、インゲン豆、きな粉、丸干しなどが挙げられます。
- 鉄分サプリメント: 高用量の摂取は吐き気や便秘などの胃腸の副作用を引き起こす可能性があるため、医師と相談することが重要です。子供の鉄中毒の主要な原因にもなりうるため、保管には注意が必要です。
- タンパク質: 赤血球やヘモグロビンの材料となります。一度に大量に摂取しても体内に貯蔵できないため、毎食摂取することが推奨されます。
- タンパク質を多く含む食品: 魚介類、肉、卵、チーズ、ミルク、牛乳、大豆製品など。
- ビタミンC: 非ヘム鉄の吸収を高める働きがあります。
ほうれん草のソテーにレモン汁など。 - ビタミンCを多く含む食品: 果物(柑橘類、いちご等)、野菜、イモ類など。
- 葉酸・ビタミンB12: 正常な赤血球を作るために必要であり、欠乏すると悪性貧血が生じます。
- 葉酸を多く含む食品: 肉(レバー)、豆類、緑黄色野菜など。
- ビタミンB12を多く含む食品: 肉類(レバー)、魚介類、卵、乳製品など。
- ビタミンE: 欠乏によって軽度の溶血性貧血が生じることがあります。
- 亜鉛: 欠乏により赤芽球の分化・増殖が障害されて貧血が生じることがあります。スポーツ競技者や透析患者では、亜鉛欠乏性溶血により貧血になることがあります。
- 銅: 不足すると鉄投与に反応しない貧血が起こることがあります。
5.3. 医療的介入
- 鉄剤・ビタミン剤の処方: 貧血の原因や程度に応じて処方されます。鉄剤の場合、貧血はすぐに改善しますが、貯蔵鉄を考慮し3ヶ月間は服用を継続することが推奨されます。
- 止血処置: 出血が原因の場合は、止血剤の使用や内視鏡治療、手術による止血が試みられます。消化管からの出血では、黒色便(食道、胃、十二指腸からの出血)や血便・鮮血便(小腸、大腸、直腸、肛門からの出血)として現れることがあります。黒色便の方が失血量が多い傾向があります。
- 輸血: 出血などで急速に貧血が進行する場合や、慢性的な貧血で日常生活に支障がある場合に、症状改善のために行われます。
5.4. 日常生活での工夫(特にがん患者向け)
- 転倒注意: めまいやふらつきによる転倒を防ぐため、急な立ち上がりを避け、手すりを使うなどの工夫が必要です。
- 自身の血液データと症状の把握: ヘモグロビン値と自身の症状の関係を把握し、体調変化に気づきやすくすることが重要です。
- 休息の確保: 倦怠感が強い場合は、こまめに休息を取り、昼夜のリズムを整えることが疲労回復に効果的です。
- 適度な運動: 体調が許す範囲でストレッチやウォーキングなどの軽い運動を行うことも、倦怠感の軽減に役立ちます。
- 周囲の協力: 症状が日常生活に影響する場合は、家族や友人に協力を求めたり、福祉サービスを利用したりすることを検討しましょう。
6. 医療機関への受診目安
- 健康診断などで貧血を指摘された場合は、まずは内科を受診しましょう。
- 立ちくらみ、息切れ、めまい、疲れやすさ、顔面蒼白、動悸などの貧血症状がみられる場合は、医師や看護師に具体的に伝えましょう。
- 手足のしびれ、知覚鈍麻、便に血液が混じる、月経ではない時期や閉経後に出血がある、吐血(特に濃い茶色や真っ赤な嘔吐物)や黒色便・真っ赤な便が出る場合は、緊急の対応が必要になることがあるため、すぐに医療機関に連絡することが重要です。
- 小児の場合、顔色が悪く、吐血、下血、黒色便などが見られる場合は救急受診が必要です。
7. 医薬品との相互作用
鉄は一部の医薬品と相互作用する可能性があります。
- レボドパ: パーキンソン病治療薬の吸収を低下させる可能性があります。
- レボチロキシン: 甲状腺機能低下症治療薬の効果を低下させる可能性があります。摂取後4時間以内の併用は避けるべきです。
- プロトンポンプ阻害剤: 胃酸の分泌を抑えるため、非ヘム鉄の吸収を低下させる可能性があります。鉄欠乏症の患者では鉄補給に対する反応が不十分となる場合があります。
これらの医薬品を常用している場合は、鉄分の状態について医療機関に相談する必要があります。