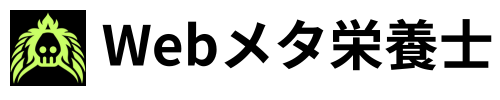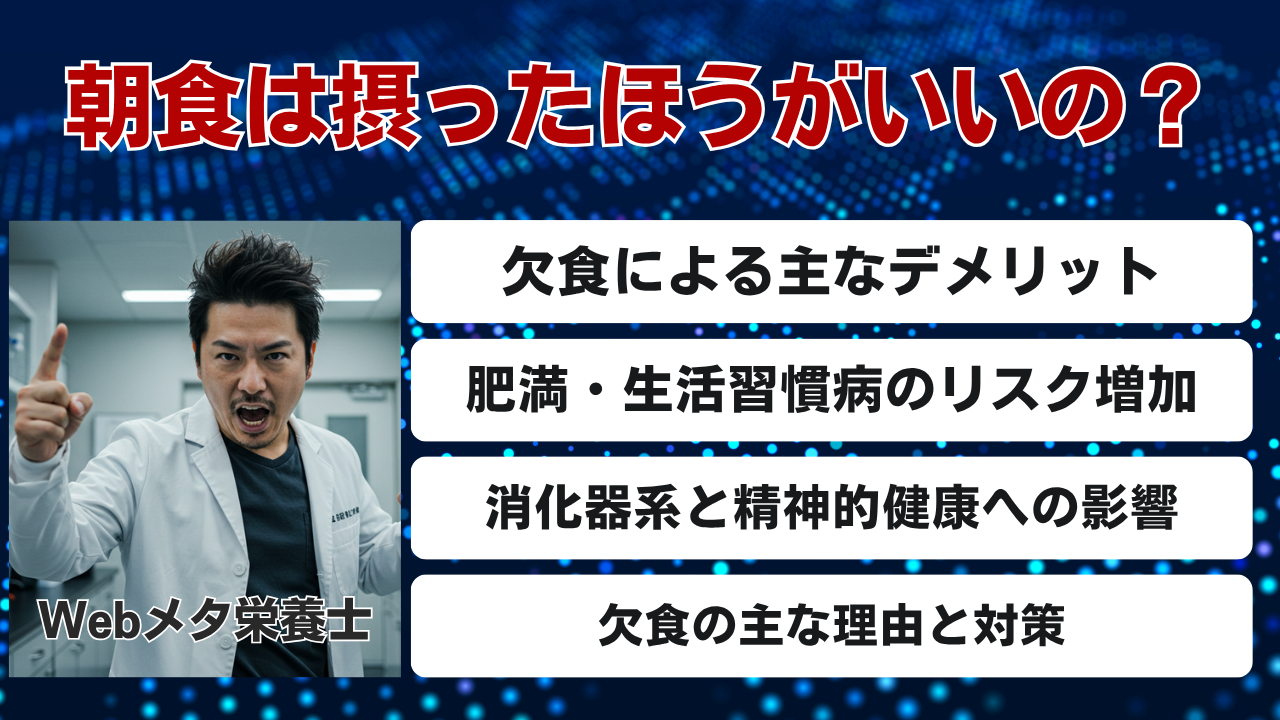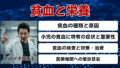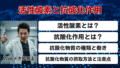朝食を抜くことは、多くの専門家や調査によって健康に悪影響を及ぼす可能性が高いとされています。むしろ、朝食は毎日摂るべき重要な食事であるとされています。
欠食による主なデメリット
朝食を抜くことには、以下のような多くのデメリットが指摘されています。
1. エネルギー不足と脳機能の低下
私たちは睡眠中もエネルギーを消費しているため、起床時はエネルギーや栄養素が不足した状態です。朝食を摂らないと、脳の主要なエネルギー源であるブドウ糖が不足し、午前中にぼーっとする、だるさや疲労感を感じることがあります。
これにより、集中力、判断力、学習能力、仕事や運動のパフォーマンスが低下すると報告されています。特に、学力テストや体力テストの結果、さらには将来の就職や収入にまで影響を及ぼすというデータもあります。
※
朝食を摂らないと、脳の主要なエネルギー源であるブドウ糖が不足しやすくなり、午前中に「ぼーっとする」「だるい」「疲労感がある」といった状態になることがあります。これは、脳はブドウ糖を大量に貯蔵できず、夜間のうちに前日の夕食で得たブドウ糖が消費されてしまうため、朝にはエネルギーが不足しやすいからです。そのため、朝食でブドウ糖を補給することは、集中力や記憶力の維持、やる気の向上に役立つとされています。
一方で、「朝食を食べると胃に血流が集まり、眠くなるのでは?」という疑問もよく聞かれます。確かに、食後は消化のために胃や腸に血液が集まりやすく、一時的に眠気を感じることがあります。しかし、朝食の場合は、適切な量とバランスを守れば、血糖値が急激に上がりすぎることなく、脳や体を目覚めさせる効果が期待できます。
特に、ごはんなどの主食を中心に、ビタミンB群やたんぱく質も一緒に摂ると、血糖値の上昇が緩やかになり、長時間にわたり安定して脳にエネルギーが供給されます。逆に、甘いものや精製された糖質だけを大量に摂ると、血糖値が急上昇した後に急降下し、かえって眠気やだるさが強くなることがあります。
つまり、朝食を抜くことで午前中のパフォーマンスが落ちやすくなりますが、食べ方や内容を工夫すれば、眠気を防ぎつつ脳と体をしっかり目覚めさせることができます。
2. 肥満・生活習慣病のリスク増加
朝食を抜いて長時間空腹状態が続くと、その後の昼食や夕食で血糖値が急激に上昇しやすくなり、太りやすくなります。これは体がエネルギーを脂肪として蓄えようとするためです。
血糖値の急激な乱高下(血糖スパイク)は、糖尿病、高脂血症、高血圧、脳心血管系疾患などの生活習慣病のリスクを高めることが明らかになっています。
「プチ断食ダイエット」や「16時間断食ダイエット」といった朝食を抜く方法が一部流行していますが、これは健康上の重大なリスクを伴うと医師が警告している例もあります。これらの食事制限を行う人では、血液検査の数値や代謝の状態が良好でないケースや、痩せていても中性脂肪が高かったり脂肪肝になったりするケースが少なくありません。
1日2食を推奨する医師の中にも、血糖値スパイク(食後の急激な血糖値上昇)についてはリスクを認識している人が多いです。
一般的な医学的知見としては、朝食を抜いた場合、次の食事(昼食や夕食)で血糖値が急上昇しやすくなり、インスリン分泌が増えたり、血管への負担が大きくなることが知られています。
実際、1日2食や1食の食事パターンでは、
- 空腹時間が長くなり、次の食事で一度に多くの糖質を摂取しやすい
- その結果、血糖値の変動幅が大きくなりやすい
- 特に糖尿病やインスリン抵抗性がある人では、血糖コントロールが乱れやすい
といった指摘があります。
一方で、1日2食を推奨する医師の多くは、以下のような考え方や対策を取っています。
- 食事の内容や食べ方を工夫する
血糖値スパイクを防ぐために、食物繊維やたんぱく質を先に摂る、糖質を控えめにする、ゆっくりよく噛んで食べるなどの工夫を重視しています。 - 総カロリーや糖質量を抑えることが最優先
空腹時間が長くなっても、1回の食事量や糖質をコントロールすれば血糖値の急上昇を抑えられる、という立場を取る人もいます。 - 健康な人や肥満傾向の人にはメリットがある
インスリン分泌や血糖コントロールに問題がない人であれば、1日2食でも大きな健康リスクはないと考える医師もいます。
ただし、医学的には「食事回数を減らすことで血糖値スパイクが起こりやすくなる」ことはエビデンスとして確立しており、特に糖尿病や生活習慣病のリスクがある人には推奨されません。
1日2食を実践する場合も、食事内容や食べ方への十分な配慮が必要であり、万人向けではないというのが現状です。
3. 体温調整と体内時計の乱れ
朝食を摂ることで消化管が動き出し、睡眠中に低下した体温が上昇し、一日の活動への準備が整います。
人間の体内時計は24時間より少し長いため、朝日を浴び、朝食を摂ることでリセットされます。朝食を抜くと体内時計が乱れ、寝起きが悪くなったり、夜の睡眠の質が低下することにつながります。
4. 消化器系と精神的健康への影響
朝食は、食べ物が胃に入ることによる大腸の蠕動運動の活性化を通じて、規則的な排便リズムを作り、便秘予防に役立ちます。腸内環境が良好に保たれることで、免疫機能も向上すると考えられています。
朝食を毎日食べる人は、ストレスを感じにくい傾向にあり、「イライラする」「集中できない」といった訴えが少ないことが報告されています。また、朝食をほぼ毎日食べる人は、そうでない人に比べて幸福度が高いという調査結果もあります。
5. 筋肉量維持とフレイル予防
朝食を抜くと、エネルギー源として筋肉や骨のタンパク質が分解され、筋肉の減少や骨の脆弱化を招く可能性があります。これは基礎代謝の低下や太りやすさにもつながります。
人生100年時代においては、筋肉維持に必要なタンパク質を摂取するためにも、朝食を含む1日3食の摂取が「フレイル予防」に非常に重要です。
※よければ以下記事もご覧になってください。
「サルコペニア」「フレイル」「ロコモ」
欠食の主な理由と対策
「時間がない」「元々食べる習慣がない」「少しでも長く寝ていたい」などが朝食を抜く主な理由として挙げられています。しかし、これらに対する対策も提案されています。
- 準備の工夫と時短:
- 前日の夕食のおかずを多めに作って朝食に回す。
- あらかじめ小分けにして冷凍したご飯を活用する。
- 果物やヨーグルトなど、調理不要ですぐに食べられるものを常備する。
- インスタント食品やカット野菜を上手に活用する。
- 朝食のパターンを決めておくことで、メニューを悩む手間を省く。
- ご飯やおかずをワンプレートに盛り付けると、洗い物が減り、見た目も楽しめます。
- 前日の夕食のおかずを多めに作って朝食に回す。
- 習慣化のヒント:
- 「ご飯+1品」から始めるなど、無理のない範囲で少しずつ習慣化を目指しましょう。まずはバナナやヨーグルトなど、何かを口にすることから始めるのも良いでしょう。
- 食欲がない場合は、消化の良いものを選んだり、夕食を分食したりする工夫が有効です。また、早寝早起きを心がけ、朝食を食べる時間を作ることも大切です。
- 「ご飯+1品」から始めるなど、無理のない範囲で少しずつ習慣化を目指しましょう。まずはバナナやヨーグルトなど、何かを口にすることから始めるのも良いでしょう。
- 理想的な朝食の内容:
- 「1日3食のバランスのよい食事」**が基本とされ、プレートの半分を野菜と果物、主食とタンパク質を同量にすることが推奨されています。
- 主食は、パンよりGI値が低い「米」(特に玄米、胚芽米、雑穀米など)が脳の発達に良いとされています。
※よければ以下記事もご覧になってください。
GI値 - 脳の機能を最大限に引き出すためには、ブドウ糖だけでなく多様な栄養素を摂るためにおかずの種類を増やすことが重要です。ヨーグルト、牛乳、味噌汁、卵料理、果物、野菜副菜、納豆などの発酵食品、前日の残り物などが推奨されています。
- 動物性タンパク質は魚、鶏肉、豚肉、牛肉の順に選ぶことが推奨され、加工肉は控えるべきとされています。
※加工肉の中で最も健康に悪いとされる種類は、特に「ハム」「ソーセージ」「ベーコン」などの高頻度で消費される製品です。これらは保存や風味のために亜硝酸ナトリウムなどの発がん性が指摘される添加物が多く使われており、発がん性リスクが高いとされています。
ただし、日本では食品衛生法により、ソーセージなどの加工肉に含まれる亜硝酸塩の残存量には厳しい上限(0.070g/kg以下)が設定されており、通常の食生活で直ちに健康被害が出るわけではありません。また、最近では亜硝酸塩の使用量が少ない製品や、「無添加」や「低添加」をうたう加工肉も増えています。 - 人工甘味料や食品添加物を減らし、良質な原材料の調味料(塩麹や味噌など)を選ぶことが、腸内環境の改善につながります。
- 「糖質オフ」よりも「糖質の種類を選択」すること(白米から玄米など)や、「カーボラスト」(糖質を最後に食べる)などの食べ方の工夫で、血糖値の急激な変動を抑えられます。
しかし、カーボラストと言われても、例えばお肉だけを先に全部食べてしまうと、ご飯のおかずがなくなってしまい、食事の満足感や楽しみが減ると感じる方が多いです。この点については、専門家や管理栄養士も現実的な工夫を提案しています。
実際には、最初にサラダや野菜を食べる「ベジファースト」から始めるのが最も現実的かつ効果的とされています。野菜に含まれる食物繊維が、糖質や脂質の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を抑えてくれるためです。
また、「野菜→たんぱく質→糖質」の順番が理想ですが、厳密に守る必要はなく、まずは野菜を最初に食べることから始めるだけでも十分なメリットがあります。
まとめると、「おかずだけ先に食べる」のは現実的ではないので、まずはサラダや野菜を最初に食べることを意識し、その後におかずとご飯をバランスよく食べ進める方法が、無理なく実践できておすすめです。 - 「ひとくち30回噛んで、ゆっくり食べる」ことも、満腹中枢を刺激し、血糖値の急激な上昇を防ぐために推奨されています。
- 「1日3食のバランスのよい食事」**が基本とされ、プレートの半分を野菜と果物、主食とタンパク質を同量にすることが推奨されています。
まとめ
朝食は、単なる一日の始まりの食事ではなく、身体的・精神的健康、学力、仕事のパフォーマンス、さらには将来の収入や幸福度にも大きな影響を与える極めて重要な要素です。
身体的・精神的健康や学力、仕事のパフォーマンスが将来の収入に影響を与える理由は、複数の調査や研究で示されています。
まず、健康的な食習慣や生活習慣を持つ人は、集中力やモチベーションが高く、仕事や勉強で高いパフォーマンスを発揮しやすい傾向があります。たとえば、朝食を毎日食べる習慣がある人は、仕事への意欲や集中力が高く、その結果として収入も高くなる傾向があることが東北大学の調査などで示されています。
また、健康的な生活習慣を持つ人は、生活習慣病やメンタルヘルスの問題が少なく、欠勤や早期退職のリスクも低くなります。これが長期的に見ると、安定した就労やキャリア形成につながり、結果的に生涯年収が高くなる要因となります。
さらに、所得と健康習慣には相関があり、健康的な食生活や運動習慣を持つ人ほど、肥満や病気のリスクが低く、仕事の生産性も高いという傾向が報告されています。
要するに、健康的な食習慣や生活習慣は、学力や仕事の成果を高めるだけでなく、長期的には安定した収入や高い生涯年収にもつながる重要な要素だと考えられています
安易なダイエット法としての朝食抜きは健康上の重大なリスクを伴うため避けるべきであり、バランスの取れた「1日3食」を基本とし、食材の質や食べ方にも意識を向けることが、人生100年時代を健康に豊かに生きるための鍵となります。